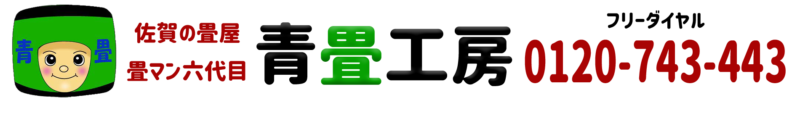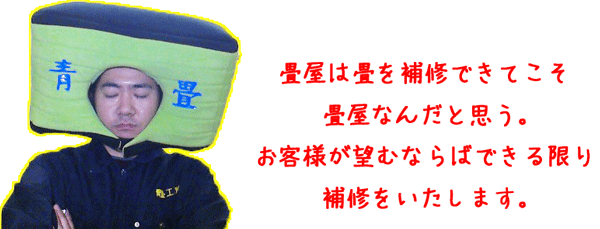畳マン六代目です。江戸時代から続く畳職人の家系に生まれ、畳製作一級技能士として長年畳に関わってきました。
お見積もりの際に見本を持ってお客さん宅を伺うと、「見ても素人にはわからないよ」と言われることが多いのですが、皆さん必ず違いがわかります。
盲目の方のお宅へもお見積りに伺うことがありますが、触り心地だけでも品質の差を理解することができます。それほどに畳表には品質の差があるのです。
今回は、畳職人としての経験と専門知識をもとに、普及品と上級品の畳表を比較し、その違いを詳しく解説します。
畳の見た目と質感の違い
畳表の品質は、見た目や触り心地に大きく影響します。
普及品と上級品の見た目
こちらが普及品の畳表を使用した畳の框(かまち)部分の画像です。特に品質が悪いというわけではなく、あくまでも普及品レベルのものです。

では次に、上級品の畳表を使った畳の框部分を見てみましょう。

比べてみると、一目瞭然の違いがわかるかと思います。
-
普及品は表面にザラつきがあり、光の反射でムラが出ることがある。
-
上級品は表面がきめ細かく、滑らかに光を反射する。
また、上級品は経年変化による色の変化が穏やかで、美しい風合いを長く保つことができます。時間が経つにつれ、黄金色に変わるのも特徴のひとつです。
さらに、上級品の畳表は光の当たり方によって微妙な表情を変えることがあり、部屋の照明の影響を受けにくい特徴があります。これは、織り密度や使用されるい草の質が関係しています。
畳縁に近づくほど・・
畳縁を縫い付けた後の普及品(上)上級品(下)の画像です


畳縁(たたみべり)をつけると、さらに品質の違いが顕著になります。
-
普及品の畳表は、畳縁に近づくとい草が少し白っぽく見えてくることがわかるでしょうか?
-
上級品の畳表は、色が均一で統一感があります。
これは、畳表がい草の穂先と根の方を交互に織るためです。い草の長さが短いと根の白い部分が出てくるため、畳表の色ムラが生じます。また穂先は枯れやすいため、赤みがかった色が混ざりやすくなります。
安いものほど短いい草を使用している場合が多いため下級品ともなればもっとはっきりとした色むらが出ます。
また、い草を織る前に長さで選別を行いますが、長いものほど育成期間がほぼ均一で、短いものほど新芽と古いい草が混ざるため、色の統一感が失われやすくなります。
さらに、両者の畳表を比べると、畳目の谷の部分の深さにも違いがあります。
これは、い草の本数(詰まり)が違うことや、中の縦糸の綿糸や麻糸の違い、織機の地締め(じじめ)と呼ばれる部分の調整によって変わってきます。
一般的に、普及品よりも上級品のほうが谷目が深く見え、「絞り目」と呼ばれる状態になりやすいです。
織りの違いが生み出す品質差
畳表は、い草を織る工程によっても品質が左右されます。
い草の詰まり具合
畳表の良し悪しには、い草の本数(詰まり)も関係してきます。
-
普及品 → い草の本数はそこそこ。一畳あたり4000本〜程度
-
上級品 → い草がしっかり詰まっている。7000本前後
また、畳表の谷の部分(畳目の深さ)も、
-
普及品は谷目が浅く、平坦な印象。
-
上級品は谷目が深く、繊細な陰影が生まれる。
この「絞り目」と呼ばれる状態は、畳の高級感を決めるポイントの一つです。
織り密度が高いほど、畳表は丈夫で長持ちしやすくなりますが、詰めすぎもい草そのものの良さを潰してしまうため良くありません。何事もちょうどいいが存在します。
畳の品質を選ぶ際には、この織りの密度と降り上がりの滑らかさにも注目しましょう。
まとめ:良い畳表を選ぶポイント
畳表の品質を見極めるポイントは以下の通りです。
-
見た目の均一感 → ザラつきがなく、滑らかかどうか。
-
畳縁との境目 → 白っぽくならず、統一感があるか。
-
い草の長さ → 一般に長いい草が良いとされる
-
畳目の深さ → 谷目が深いほど陰影がはっきりする。
-
縦糸の種類 → 麻糸の方が耐久性が高くなるものが多い。
-
経年変化の美しさ → 色味が均一なものは日に焼けても均一な黄金色に。
実際に畳表を選ぶ際は、これらのポイントを確認すると、より良い畳を選べます。
畳選びは、ぜひ品質に注目してみてください。