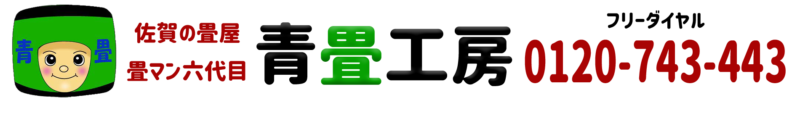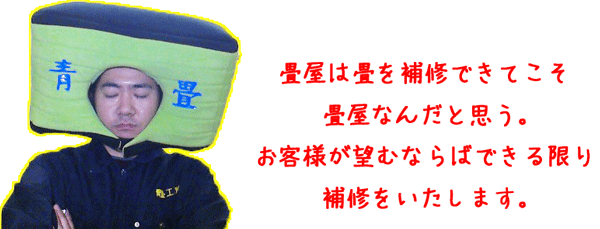畳替えのご縁があったお寺さんに住職さんが座る礼盤畳を寄贈してきました。
製作方法は略式の上ゴザ無しのタイプです。
使用した畳縁は白中紋です。


仕事の内容にもよりますが、ご縁があったお寺さんには出来るだけお寺の宗派に合わせて、礼盤か、四天拝敷き等を寄贈しています。
そして新しくした礼盤畳の前に使われていた古い礼盤畳を処分するとのことで引き取ってきました。
その裏の画像です。

もともとかなり昔に作られた礼盤を何度か張替えているようでした。
が、、前回の畳屋さんの作り方が酷すぎるというか作り方を知らないんだろうなというお粗末すぎるもの。
縫わずにタッカーを使って秒で止めてあります。。そのおかげで茶色い点はタッカーの錆がでてます。
縁は織物ではなく印刷の物・・。
この裏面の畳表なんと中継ぎ表と言われる今では貴重な織り方の畳表。裏返ししたゴザのようで中継ぎ特有の裏側に出るイグサを上手に毟ってありました。
恐らくは、この礼盤の数回に及ぶ表替えの初期からついていたようです。
しかしタッカーは何にもいいことないので遺憾ですね。本当、佐賀のお寺さんではこんなんばっか見ます。
まともに作れる畳屋はほとんどいないのか??
ちなみに今回畳マン六代目が製作して寄贈した礼盤の裏側の仕上げ↓

もちろんタッカーなんて使ってませんし、裏でもできる限り綺麗に紋が出るようにつくりました。
住職さんはこの仕上がりを見て、裏も使えるねって言われました(笑)
でも裏は裏ですけどねw
住職さんは、今まで他のお寺さんに前の礼盤を見られるのが恥ずかしくて堪らなかったといっておられました。
喜んでいただけたので寄贈した自分も嬉しくなりました^^
さて、中継ぎ表に気付いた私が、芯材がどうなっているかきになるので、これを解体しない訳がありません(笑)
裏側の中継ぎ表を剥がすと

やっぱり!!手床だ!!
手縫い畳床の作り方でいうと、「筋縫い」という畳床でした^^
さらに解体を進め、表側を剥がすと、礼盤の厚み調節の為か、丹波表がでてきました!!
そこにもビックリしましたが、表側の畳床は裏と種類が違う!!
今回の礼盤は畳の厚みが約2枚分の二畳台ですので、畳床を重ねて使ってあるのです。

なんと!これは珍しい!棒縫いの手床が出てきました。
古床で棒縫いが出てきたのは初めてでビックリ!
裏面の筋縫い畳床よりも簡易な作り方になる棒縫い畳床ですが、おそらく裏表の畳床は作られた年代が全く違うのではないだろうかと推測。
古い畳を解体して、その畳床を切り合わせて礼盤畳を作ってあることも多々あることです。
しかし畳床の構造を見た瞬間に手床の名前がわかるなんて・・・本当に山口県の荒川さんに手床を習っていて良かった~♪