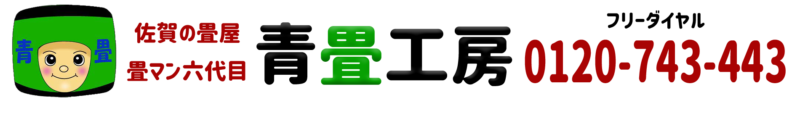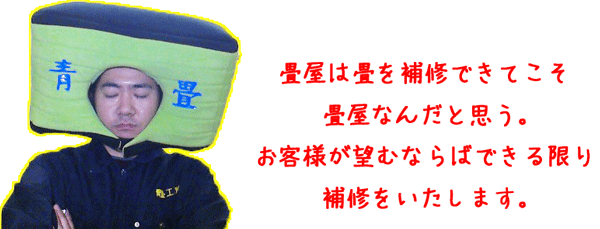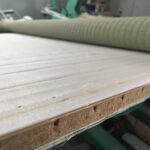こんばんは、畳マン六代目です!江戸時代から続く畳屋の技を受け継ぎ、日々畳の製作を通じて、皆さんの快適な生活を支えています。👋
今日は、「畳の敷き方」について話をしましょう。なんと、畳には向きがあるんですよ!😲
しかも、その向きを間違えると畳がゆがんだり隙間ができたりするなど、思わぬトラブルの元に。
そんなトラブルを避けるためには、畳の裏に書かれた「裏書」を見ることが大切です。
この記事を読んで、畳の敷き方のコツを学び、快適な和室ライフを楽しみましょう!✨
畳の敷き方: 位置だけではなく向きも重要! 👈

和室の畳の敷き方はただ適当に敷くだけではなく、位置だけでなく向きも重要なんです!
必ず畳の裏に書かれた文字を見てください。
「畳に向きがあるの?」と思うかもしれませんが、これが実は大切なポイントなんです。🔍
畳の向きを間違えると…
先日、お客様のお宅で畳の表替えをするために伺ったところ、6畳間で4枚が逆向きに敷いてあったんです!😲
向きが違うと畳の目がおかしかったりするので畳屋さんは違和感を感じ取り大抵すぐに気づくものなんですよ。
もし畳の向きが間違っていると、畳がゆがんだり、隙間ができたり、高さが合わずに擦れたりなど、さまざまな問題が起こります。
畳の向きを確認する方法は?
では、どうやって畳の向きを確認するのでしょうか?
それは簡単、畳の裏に書かれている裏書(方書)を見ることで解決します。📝
例えば、「西北」という裏書があったとしましょう。これは、西側にある北に付いた畳ということを示しています。
畳縁が西側で、畳縁がない短い辺が北にくるということなんです。✅
でも注意点があります。畳縁は畳に二本通っているので、どっちを内側に、どっちを外側にするのかが重要。
間違えてしまうと畳そのものの場所は合っていても、畳が無理に押し込まれたり、隙間ができたりします。💦
「西北」などの他「西川北」と書かれている場合も同じ考えで西側(川)の北付きの畳となります。
上記はあくまで当店がある地域での多い書き方になるのですが、
地方により個性があり、佐賀から出るとまた全然違う書き方のこともありますのでご容赦ください。
畳の敷き方のコツ
それでは、どうすれば畳を正しく敷くことができるでしょうか?
ここで畳には「上前」と「下前」があるということを覚えてください。裏書の文字の頭部分が「上前」になるんです。
そして、この「上前」を部屋の内側にくるように敷くと基本はOK!これが畳の敷き方のコツなんです。✨
畳マン六代目の考察: 畳の裏書について🤔
畳の裏書については、畳屋だけでなく一般の方や床下点検する大工さん、シロアリ屋さんにも一発でわかるような風にしていくべきだと考えています。
もちろん、私もその一人で、これからの裏書作りについて考えさせられる瞬間でした。
ですが、人間なんて面白いもので、そういったことを考えた直後にはすぐ忘れて、ついつい普通に裏書をしてしまうんですよね(笑)。
裏書の文字が達筆すぎて読めなかったり、もっと専門的な言葉で書かれていることがあります。
「手先」「手元」などの裏書になると意味が分からなければあっという間に忘れてしまうでしょうね。
「手元」は畳屋さんが畳を縫うときに使う言葉で、縫い始める側、「手先」は縫い終わる側。
基本畳は右から縫い始め左に進みますので、畳の場所としてもそういういう意味になります。
裏書が読めない理解できない時は、畳を外す時に自分流でちょっと印や場所を書いてみてくださいね!
最後に:畳の向き、確認しましたか?
今回の記事を通して、畳の向きの重要性と確認方法について説明しました。敷き直した畳の向きが間違っていると、畳がゆがんだり高さが合わずに擦れたりする原因になるため、畳を剥がすことがあったら是非とも畳の向きをチェックしてみてください。
畳マン六代目として、これからも皆様の快適な暮らしをサポートするため、畳に関する情報を発信してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。🙇♂️🍃