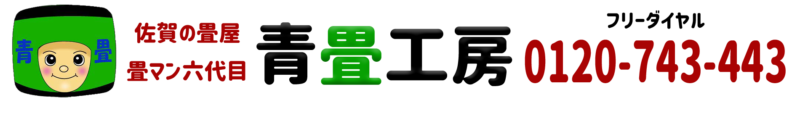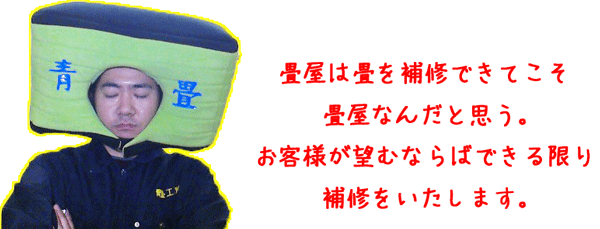こんにちは、畳マン六代目です。
創業170年以上の歴史を持つ老舗畳店の六代目として、“国産い草のみ”を扱い、「本当に良い畳」にこだわり続けてきました。
畳製作一級技能士としての経験から、多くのお客様からよくいただく質問がこちらです。
「畳の価格って、どうしてこんなに違うの?」
「高級といわれる畳と安い畳、具体的にどこが違うの?」
「失敗しない畳選びのコツは?」
一言でまとめると、畳の価格は“い草(畳表)”の質と織り方、そして畳床や職人の技術で大きく変化します。
ただ、残念ながらそれを十分に説明しないまま「どれも似たようなものですよ」と売っている畳屋さんもあるのが実情。
ここでは、畳の価格差を生む具体的な要素と、良い畳を選ぶために押さえておくべきポイントを深掘りしてご紹介します。
◆ 畳の価格が決まる主な3つの要素
- 畳表の品質
✅ “い草”の産地・長さ・太さ・織り方・色合い・選別具合 - 畳床(芯材)の構造
✅ 本畳(わら床)・建材畳・複合床など - 施工技術(職人の腕)
✅ 縫着の仕上がり、ヘリの処理、美観・耐久性へのこだわり
このうち、特に「畳表(い草)」が価格や品質に直結するため、い草について詳しく理解することが“良い畳”を選ぶうえで欠かせません。
◆ なぜ「い草」が鍵?その理由と品質の見極めポイント
1)産地だけでは判断できない“い草”の選別
「熊本県産のい草を使っています」という謳い文句はよく聞かれますが、実際には同じ産地でもピンからキリまで品質はまちまち。
い草は収穫後に選別作業を行い、「長さ」「太さ」「色」などを基準に等級分けされます。
この選別工程がしっかり行われているかどうかが、「品質」の大きな分かれ道です。
- 長さが揃っているほど、織ったときにムラが出にくく美しい表面に。
- 太さが均一だと、踏んだときの感触が滑らかで上品。
- 色合いに変色や斑(むら)が少ないほど、焼けた後も美しい黄金色に変化。
- 織りの密度が極端に高すぎると、い草が潰れてかえって耐久性が落ちる場合も。
2)詰め込めば良いわけではない?い草の“ハニカム構造”
い草は内部が“蜂の巣状(ハニカム)”になっており、この空気層があることで調湿効果やクッション性を生み出しています。しかし、
✅ 織りをギュウギュウに詰めすぎる
✅ い草を無理やり押し潰してしまう
と、ハニカム構造が壊れ、呼吸する力が減少してしまうのです。
- い草本来の機能
✅ 足ざわりの柔らかさ
✅ 湿気の吸放出による快適性 - 詰め込みすぎることで失われる可能性アリ
✅ 高級畳のつもりが、実は逆効果になるケースも…
3)安い“国産い草”もある?その落とし穴
国産い草を使っていても、
- 下位等級のい草を混在させたもの
- 選別が甘く、短いい草が多い
- 色ムラや傷が多い部分をそのまま織り込んでいる
といったケースでは、見た目にも耐久性にも問題が生じやすいです。
「国産なら安心」と思いこまず、実際の畳表を見比べることが大切になってきます。
◆ 畳床の違いも価格に影響!「本畳」vs「建材畳」
い草を織った畳表の下には、畳床(芯材)があります。
伝統的な“わら床”を用いたものを「本畳」といい、昔ながらのクッション性や調湿性が期待できます。
一方、現代住宅向けには、発泡樹脂や木質ボードを組み合わせた“建材畳”や、わらとボードを複合したものも存在します。
- 本畳(わら床)
✅ 弾力があり、踏み心地が良い
✅ 重量があるため音や振動を吸収しやすい
✅ ただし、湿気が多い場所ではカビやダニ対策が必要 - 建材畳(ボード系)
✅ 防湿性や軽さがあり、マンションなど高層住宅にも適合
✅ 耐久性が高いタイプもある
✅ 踏み心地はわら床に比べるとやや硬め
畳床の種類によって、価格・性能・メンテナンス性が変わるため、どちらを選ぶかは住まいの環境やお好みに左右されます。
◆ 職人の技術が畳の“寿命と仕上がり”を左右する
1)目に見えない仕込みの丁寧さが重要
い草や畳床がどんなに高品質でも、縫着が雑だったり、ヘリの仕上げが甘かったりすると、本来のポテンシャルを活かしきれません。
実は“見えない裏側”の処理こそが畳の耐久性を大きく左右します。
- ✅ 古い糸やステープルをきちんと除去しているか
- ✅ 畳床の凹みや段差を補修しているか
- ✅ 縫着のテンションが適正か(強すぎも弱すぎもNG)
2)ヘリの処理や角の仕上げで職人の腕がわかる
畳のヘリやコーナーの部分は人目に触れやすく、また傷みやすい箇所でもあります。
角がピタッと合っているか、糸の留め方は丁寧かといった細部にこそ、プロの技術が光るもの。
高級畳は見た目の美しさだけでなく、長年使っても崩れにくいメリットがあります。
◆ 良い畳を選ぶための5つのポイント
- 畳表の見本を見せてもらう
▶️「国産い草」といっても等級がさまざま。実際に触れて織りの密度や色合いをチェック。 - い草の長さ・太さ・色ムラの説明を受ける
▶️ 希望予算に応じて、どのランクのい草を使うのか明確化。 - 畳床の種類を確認
▶️ 本畳が良いのか、建材畳が良いのか、住環境や防湿面から考えて選ぶ。 - 仕上がりのイメージを詳しく聞く
▶️ カラー畳やヘリ無し畳など、デザイン面のバリエーションも事前相談を。 - 施工実績やアフターフォローをチェック
▶️ 職人の技術力・口コミ評価・納品後のメンテナンス体制を確認。
◆ まとめ:本当に価値ある畳を選ぶために
- ✅ 畳の価格差は「い草(畳表)の選別・織り方」「畳床」「施工技術」が大きく影響
- ✅ い草は産地だけでなく“選別”が命。長さ・太さ・色・織り密度を見極める必要
- ✅ 織りの詰め込みすぎは逆効果。い草のハニカム構造が潰れ、機能低下の恐れ
- ✅ 畳床もわら床か建材床かによって、足ざわり・防湿性・価格が変わる
- ✅ 職人の技術が仕上がりの美しさと耐久性を左右
- ✅ 良い畳屋さんは見本やランクを丁寧に説明し、アフターケアも万全
和室を快適に保つうえで、畳選びはとても重要。長いスパンで見ると、高品質な畳にしておけば「すぐに傷んで交換…」という事態を避けられ、トータルでコスパが良いケースも多いです。
「いろいろ話を聞いてもどれがいいのか分からない…」「適当に選んで失敗するのは嫌だ」という方は、ぜひ畳マン六代目(青畳工房)までお気軽にご相談ください。
長年培ってきたノウハウと、高品質な国産い草へのこだわりで、あなたの理想の和空間づくりをサポートいたします!
本当に良い畳を選んで、快適な和室ライフを手に入れましょう。