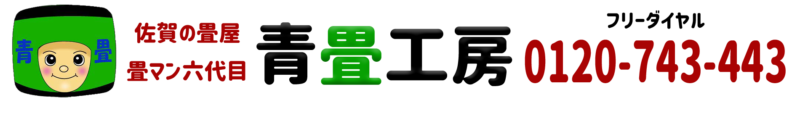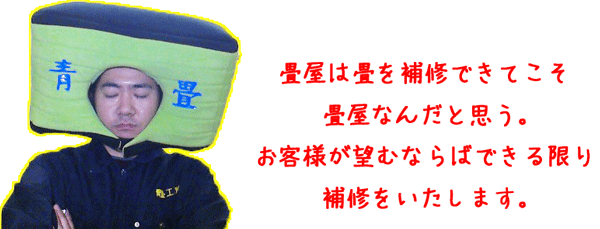皆さん、こんにちは!👋 畳マン六代目こと、江戸後期から続く畳屋六代目、青畳工房の一級技能士です!
茶室の畳について一緒に深掘りしていきましょう!
日本文化の花である茶室の畳、それは炉畳から台目畳まで、その一つ一つに実はたくさんの秘密と知識が詰まっています。
この記事を読むことで、少しだけでも茶室の奥深い文化や伝統をより深く理解し、畳の色合いや茶室の雰囲気についても探求していきましょう!
皆さんが茶室の畳に対する興味を深める手助けとなれば幸いです。
さあ、一緒に畳の世界を旅しましょう!🍵💼
茶室の畳ついて知っておこう: 炉畳から台目畳まで 🍵
茶室というと、何となく日本文化の深淵を覗き見ているような気がしますね。
畳マン六代目としては、その深淵の中には古い畳の知識が詰まっているのが実に興味深いのです。
今日は、炉畳や台目畳といった茶室の畳について解説します。👍

炉のある炉畳について 🍵
茶室と言えば、その一角には炉があることが一般的です。この炉が設けられている畳を特に「炉畳」と呼んでいます。
炉畳は、縦横1尺4寸(約42.5cm)をくり抜いたような形になっていて、その加工具合が畳職人の技術を試される瞬間でもあります。😓
炉縁(炉の枠)を外して、同じ大きさの畳をはめ込むことで、炉の穴を畳で塞ぐことが可能なんですよ!💡
炉を使う/使わないを選択できるようになります。
茶室における台目畳の存在 🍵
次に、茶室の畳の話といえば、「台目畳」も欠かせません。
台目畳とは、通常の茶室の畳の4分の3ほどの長さがある畳のことを指します。📏
台目畳が存在することで、茶室に独特の奥行き感や広がりをもたらします。
茶室の畳替え、採寸が大変ですが… 🍵

茶室の畳替えは、一見単純に見えますが、採寸が少し大変な作業となります。📏
特に写真のように炉だけではなく、床の間から伸びた木の枝のような箇所の部分があると、さらに複雑になります。
お部屋の四隅が完全に直角で、全ての壁が並行であるというのは、残念ながら現実にはありません。
木の曲がりや、角の微妙な角度の違いなど、さまざまな要素が複雑に絡み合って、畳一つを作るだけでも難易度が上がります。🧐
しかし、その細かい角度や距離を丁寧に計測し、採寸した寸法通りに畳を作ることで、ようやく綺麗に畳を納めることができます。
これこそが一級技能士、畳マン六代目の真骨頂と言えるです💪
畳の色合いと茶室の雰囲気 🍵
さて、話は少し変わりますが、茶室の畳の色合いについても触れておきましょう。
特に茶室では、畳のヘリ(縁)の色をどうするかは重要な要素となります。
一般的には、落ち着いた色味のもの(黒、茶、紺色など)が多く用いられ、茶室全体の雰囲気を引き立てる役割を果たします。🎨
まとめ: 茶室の畳には多くの工夫がある 🍵
いかがでしたでしょうか。
茶室の畳には、一見すると気付かないような苦労や技術がたくさん詰まっています。
炉畳や台目畳など、その役割や特性を理解することで、茶室が持つ奥深い文化や伝統に思いを馳せることができるのではないでしょうか。
茶道に精通しておればもっと詳しく解説ができるのかもしれませんが、あいにく茶道は嗜んだことがなく、、
茶室の畳替えの際には、その全てを理解し、技術と情熱をもって仕事に取り組む畳マン六代目をぜひともご利用ください。それでは、皆さんの茶室でお会いできることを楽しみにしています!🙌
それでは、畳の世界でお待ちしております。